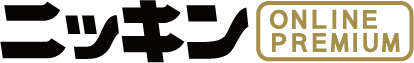みらいコンサルティングが提供するシリーズ「コンサルティングのヒント集」。経営改善をテーマに経営不振企業への支援ポイントを解説してきた。今回は、「経営改善の実現に向けたモニタリング」と題しシリーズの最後を締めくくる。
みらいコンサルティングが提供するシリーズ「コンサルティングのヒント集」。経営改善をテーマに経営不振企業への支援ポイントを解説してきた。今回は、「経営改善の実現に向けたモニタリング」と題しシリーズの最後を締めくくる。経営計画を作成しても、実際に実行し、成果を得なければ意味はありません。そのため、モニタリングというプロセスがいかに重要であるかは、想像に難くないと思います。しかし、実際にはこのモニタリングがうまくいかない、実績が計画未達というケースがよくみられます。
その原因の1つは、「計画実行に向けての当事者意識が希薄である」点があげられます。ただし、この点については社外の立場からは見えにくく、支援もしにくいものです。そこで、今回はこの「当事者意識」の問題について、特に「経営者の当事者意識」に着目して、私たちの実体験を踏まえながらお話しさせていいただきます。
まず、「経営者の当事者意識」を語るうえで、「経営者は孤独な状況のなか、多くのものを背負いながら、会社を牽引されている」点を忘れてはなりません。これに対する理解やリスペクトの念は、経営者との信頼関係構築のために必要です。
とはいえ、経営者自身の当事者意識に課題がみられるのもまた事実であり、以下のケースで問題になるといえます。
①現実を直視しない(向き合わない)
②組織内外のしがらみを抱えている(実行できない)
③現場の巻き込み力が弱い(付いてこない)
今回は②③の経営者についてもう少し説明します。
こうした経営者の方は、「自分はやるべきことをやっている」、「周りが悪い・レベルが低い」などの意識を持つ傾向にあり、実際そのような発言を数多く耳にしてきました。伴走支援が必要とされるのは、まさにこうした状況において、経営者が伴走者との「対話」を通じ、「気づき」を得て、「納得」し、「内発的動機付け」を得て、「自己変革力」を高めるためであり、その意味でも定期的に経営者と対話をする「モニタリング」は、非常に重要な場となります。
例えば、雇われ社長のケースでは、モニタリングのなかで、社長の関心が100%改善に向かっておらず、見栄えに対する過剰な意識や、色々と理由をつけて変革を拒む傾向がみて取れることがあります。
この場合、伴走者としては、そうした言動そのものを指摘するのではなく、なぜそのような行動をとるのかに関心を持ち、社長の立場を理解、共感することが重要と考えます。すなわち「傾聴」「承認」をおこない、社長の心のなかにある「障害」を共有することがスタートになるのです。
私たちが支援したケースでは、社長の〝オーナーへの遠慮や保身〟が心理的障害になっていると判断(共有)し、あえてオーナーと社長との定期面談を提案し、そこに私たちが同席することで、双方の情報共有と建設的なコミュニケーションの場を取り持つことにしました。これを継続することで、「やりやすくなった。心理的に楽になった」と、社長のリーダーシップがより発揮されるようになりました。
モニタリングは、計画の実行により成果の獲得を確実にするためのものです。そして、そのためには、成果を測定しPDCAを回すことが重要であることに間違いはありません。
しかし、うまくいかない原因は、最終的には人に起因することが多いものです。従って、モニタリングという機会を通じて、経営者との対話を深め、内発的動機付けを促すことも、伴走者の重要な役割と言えます。
ぜひ〝社長の関心〟に関心を持ってください。例えば、「改善を進めるうえで、社長ご自身にとっての悩み・障害は何ですか?」と伺ってみてはいかがでしょうか。社長の関心に触れることができれば、より多くの支援の機会がみつかるかもしれません。
 西原 和光 氏(さいばら かずみつ)
西原 和光 氏(さいばら かずみつ)シニアコンサルタント
公認会計士
監査法人を経て、みらいコンサルティング株式会社入社後は、中小企業向けにビジョン策定支援、経営改善計画策定支援、モニタリング支援など、
幅広なコンサルティング業務に従事。