【金融政策の読み筋】「日銀文学」の扉 複合〝ツール〟でシグナル発信
2023.09.22 04:40-1.jpg)
〝声明文〟から段階的に
金融政策決定会合の実施日を起点に、「ツール」をたどっていく。
情報発信の基軸となるのが(金融政策決定会合の)声明文。民間企業でいう取締役のような立場である政策委員(総裁・副総裁含め9人)が集まり、2日間に渡って開かれる同会合の終了後、速やかに公表される。1~2カ月のスパンで組まれる次会合までの政策運営に関し、政策金利や、ETF(上場投資信託)・社債といった資産の買い入れメドなど議論の「結果」が記されている。
また、2会合に1度(四半期に1度)、展望レポート(経済・物価情勢の展望)を取りまとめる。日銀による現状の景気認識などを踏まえつつ、想定する内外経済の経路や物価の先行きについて、裏付けとなる統計データとともに公表。政策委員が見通す今後3年程度の経済・物価予測を明らかにし、政策金利の上げ下げなど金融政策の方向感をつかむ重要な手がかりとなる。
会合終了当日の午後(通例では15時30分開始)には、記者会見が開かれる。総裁が出席し、声明文や展望レポートの内容に基づく記者からの質問に回答。政策決定の狙いや現状の市場動向、先行きの景気認識について「会合の議長」として発言する。
では、その会合でどんな意見が出て、議論が繰り広げられたのか。その要点が箇条書きで記されているのが【主な意見】。経済・物価や金融政策運営について、各委員の見方・考えが〝特定されない〟形で掲載。総裁が編集責任者となり、会合終了日から数えて6営業日後に明らかとなり、会合の全体観をつかむことができる。
ただ、「主な意見」では、賛同意見の数などが不明確で政策の方向性を見定める材料としては乏しい。意見の〝厚み〟を含めて議論の具体性がより詰め込まれるのが議事要旨。各論点について、「認識で一致した」「一人の委員は」との表記が意見の前後にあり、議論の収まり具合や考え方のバラつきを把握しやすい。
公表時期は会合日から一定の期間がある。1~2カ月後に開く次会合の議案にかけたのち、公表されるため、経済・市場環境が急変する局面では、記載情報の有用性が大きく落ちる。
「講演」で姿勢が鮮明になることも
政策委員が出席する懇談会は金融政策を読み解くヒントになる(岐阜県内で会見する中村豊明審議委員、8月31日)
各会合間に、全国の主要都市で開く「金融経済懇談会(金懇)」や経済団体などでの講演も、各委員の政策運営に対する見方を知るうえでヒントになる。
例えば、金懇では、総裁のほか、副総裁や審議委員が挨拶に立ち、独自の着眼点・問題意識とともに政策運営の考え方などを表すケースが多い。その後の記者会見でも、自らの言葉で足元の景気認識や物価動向を語る。
なかには、発言者が特定できない「主な意見」や「議事要旨」に記された内容と類似するニュアンスで話す委員もみられ、政策スタンスを推し量る一助になることも少なくない。
このほか、新聞・テレビといったメディアでのインタビューや、主要中央銀行トップらが集結する海外イベントの講演などでも、採りうる政策の道筋をにじませる場面が散見される。
専門用語の羅列や表現に幅を持たせる場合もあり、意図を汲み取ることが難しいことから「日銀文学」とも称される日銀の情報発信。一方、中銀が市場に深く関与した異次元緩和策の正常化が現実味を帯びるなか、日銀が発する〝シグナル〟を捉える重要度は増す。難解な文学のひも解きには、「コミュニケーションツール」の特徴を知り、情報を整理するのが第一歩になる。

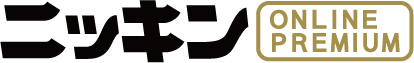
 地域版はこちら
地域版はこちら