ニッキン金融界10大ニュースにみる金融史
2022.03.01 10:33| 2010年 振興銀にペイオフ |

2010年9月10日、日本振興銀行が破綻し、戦後初のペイオフが発動された。1,000万円を超える預金は約7割が戻らない見込み。破綻の朝、3,000万円を預けていた無職の女性は、本店前で「早く解約すればよかった」と右手で顔を覆った(写真)。木村剛前会長=当時(銀行法違反容疑で逮捕)には、融資先を組織化して不良債権隠しや迂回融資をしていた疑惑も。小畠晴喜社長=当時は破綻会見で「(借り手の)感謝の気持ちを利用した」と前任者への不信感をあらわにした。金融庁は日本銀行や預金保険機構と連携して周到に準備を進め、社会的混乱を回避。現在のところ、破綻処理スキームは当局の「シミュレーション通り」に進んでいる。今後の焦点は譲渡先の選定。11年5月に第二日本承継銀行が預金や優良資産を引き継ぐが、その先の受け皿探しは「難航必至」と見られている。
2011年 東日本大震災襲う

2011年3月11日14時46分、三陸沖を震源地とする国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震が東日本を襲った。岩手、宮城、福島の3県を中心に大津波が沿岸市町村を飲み込み、死者・行方不明者19,327人(12月14日現在)に達する未曽有の大惨事に。金融機関も倒壊や浸水でピーク時320カ店が休業。ただ、当局と連携した迅速な対応で店頭での大きな混乱はなく、一部を除き店舗やATMの復旧は早かった。県外避難の被災者への預金払い戻しや支援預金、義援金、被災地でのボランティアなど全国金融機関の助け合いの輪が広がった。改正金融機能強化法による被災金融機関への公的資金注入、被災企業・個人が抱える「二重ローン」の救済がスタート。予算措置を含め復興関連法案も成立。被災地のみならず日本再生への本格的な取り組みはこれからだ。
2012年 年金消失、AIJ事件
-300x200.jpg)
企業年金から運用を受託した資産約2,000億円の約9割を消失させたAIJ投資顧問。虚偽の運用実績を謳って投資一任契約を結び、総合型の厚生年金基金を中心に被害が広がった。金融庁は2月24日、年金資産の保全を狙いに1カ月間の業務停止命令を発出。国会で証人喚問も行われ、2012年6月19日には浅川和彦・AIJ投資顧問代表ら4人が逮捕された。AIJ事件は厚年基金制度や企業年金の課題を浮き彫りにした。厚年基金制度の廃止に向けて検討されており、信託銀行によるチェック機能強化など再発防止策も動き始めた。
2013年 みずほ銀、「反社」で行政処分

みずほ銀行の反社会的勢力との融資取引問題が波紋を広げた。系列信販会社「オリコ」との提携ローンで10年に反社取引が発覚し、問題の放置や情報の担当役員止まりを理由に、金融庁は13年9月に業務改善命令を発出。しかし、みずほ銀の佐藤康博頭取=当時が10月の記者会見で問題発覚当時の経営トップにも情報が伝えられていたことを明らかにし、当局への報告が事実と異なることが判明。同行は業務改善計画を提出し、グループ役員54人の処分を決めた。金融庁は年明け以降の追加処分を検討している。一方、全国銀行協会は未然防止へ信販会社を始め金融8団体にも保有する反社情報を還元し、警察庁との反社データベースの共有化に向けた協議も再開。
| 2014年 消費税率、8%に引き上げ |
政府は4月1日、消費税率を5%から8%に引き上げた。社会保障費の財源を確保する狙い。改定は1997年以来、17年ぶり。金融機関はATM手数料などを変更。だが、貸出金利息が非課税対象のため、大きな収益圧迫要因となった。グループ内の会社間で発生する業務委託費用が増えるため、事務系子会社を吸収・解散する動きも加速。中小企業に対し、商品・サービスへの適切な価格転嫁を促す講習会を開くところも多かった。国内経済全体への影響は大きく、4~6月・7~9月の国内総生産成長率は2四半期連続でマイナスに。安倍晋三首相は11月18日、10%に引き上げる時期を2015年10月から17年4月に延期する意向を表明した。
| 2015年 改正マイナンバー法成立 |

2016年1月に運用が始まるマイナンバー(社会保障・税番号)の利用範囲を広げる改正マイナンバー法が衆院本会議で可決、成立した。18年から顧客の任意で金融機関の預貯金口座と共通番号のひもづけが開始。金融機関は今後、システム整備などを迫られる。マイナンバーは、日本に住民票を持つ全ての人に12桁の番号を付与する制度。15年10月から通知が始まった。行政機関などは、納税や社会保障給付に関する情報を一元的に把握できるようになる。金融機関も投資信託などで取引顧客から提示を受ける必要があり、態勢整備や告知を急いだ。マイナンバーを利活用し、新たなサービスの登場も期待されている。
| 2016年 日銀、マイナス金利政策導入決定 |

日本銀行はデフレ脱却に向けて、1月29日にマイナス金利付き量的・質的金融緩和の導入を決定した。金融政策としては初めての措置。日銀当座預金の一部にマイナス0.1%を適用。「量」・「質」に加えて「金利」の三つの次元で緩和手段を駆使し金融緩和を強めた。マイナス金利が適用された2月16日には、短期金融市場で取引直後から無担保コール翌日物金利が急低下、取引量も大幅縮小した。長期金利(新発10年物国債利回り)をはじめ市場金利も軒並みマイナス圏に低下。 金融機関では普通預金金利を0.001%に引き下げたが貸出金利に強い低下圧力がかかり、預貸金利ざや縮小と有価証券運用利回り低下に直結、収益環境は劇的に変化した。特に、住宅ローン金利は10年固定が0.5%以下、30年超の超長期固定型も1%割れの水準に下がり借り換えが急増。システム対応に迫られる金融機関も多く金融機関経営に大きな影響を与えた。
| 2017年 平均株価、史上初16連騰 |

17年は株価高騰が目立った。米国や欧州などの海外経済が好調なほか、国内経済も緩やかに回復。為替円安の定着のもとで日本企業の収益が過去最高水準で推移した点や底堅い日本経済のファンダメンタルズなどを海外投資家らが好感した。日本銀行の金融緩和強化に伴うETF(上場投資信託)購入も下支えした。10月には株価が16営業日連続で上昇する史上初の“16連騰”を記録。株価は21,805円となり96年7月以来、21年ぶりの水準に上昇。11月も政府の大型経済政策への期待や米国の株高などにも引きずられる形で上昇し、11月9日に年初来高値23,382円をつけた。12月も22,000円台で堅調に推移している。
| 2018年 スルガ銀、組織的不適切融資で処分 |

スルガ銀行は9月7日、第三者委員会からシェアハウス向け融資を巡り審査書類改ざんなど組織的な不正があったと認定された。これを受け同日、岡野光喜会長ら役付取締役5人全員が退任。金融庁検査では創業家関連企業への不適切融資も判明。10月5日、一部業務停止命令を含む厳しい処分を受け、創業家との決別を宣言した。
| 2019年 「令和」幕開け |
5月1日に新天皇が即位し、「令和」の時代が幕を開けた。現存する日本最古の歌集「万葉集」の梅花の歌を典拠とする248番目の元号。新時代に日本中が祝賀ムードに包まれた。金融界は、改元と10連休に伴い、顧客への周知やATMの現金補充、システムや帳票の改訂など対応に追われた。連休中には営業店を開けて窓口対応をする金融機関も。ATM画面や利用明細書で西暦表示の誤りも一部で発生したが、トラブルは限定的だった。

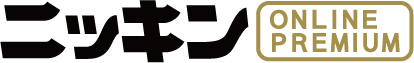
 地域版はこちら
地域版はこちら