第1回 「金融機能再考」
2021.11.08 14:12
広島銀行から通算して37年半、地域金融に深く関わり9月末をもって金融庁を定年退職しました。ニッキンONLINEの連載にあたり、読者の皆さんと我が国の戦後の金融の流れを大まかに共有することから始めたいと思います。
我が国の戦後の高度成長を支えたものの一つに、独特な金融制度があったことは間違いありません。折しもNHK大河ドラマ「晴天を衝け」で銀行の始まりが描かれましたが、明治時代に全国各地に設立された銀行は太平洋戦争の頃には一県一行に集約され、それら都市銀行や地方銀行は皆商業銀行でした。そして戦後の旺盛な設備投資需要に対応するために設立されたのが長期信用銀行であり、中小零細企業には信用組合や信用金庫などの協同組織金融機関や相互銀行が資金供給しました。さらに70年代には個人向けの住宅金融専門会社(住専)が加わり、政府系金融機関も含め細かく機能別に分化していたことに大きな特徴があったのです。
金融は社会を支える重要な機能であり、そこで期待されるものは何でしょうか。それは言うまでもなく利用する全ての人を豊かにしてさらに成長させることであり、結果的に高度成長時代にその目的は全体として達成できたと言えます。
ところが80年代の大企業の銀行離れを契機に変調を来たし、都市銀行が個人向けの住宅ローンに進出したことが機能別金融の終わりの始まりでした。住宅ローンは土地建物のみならず商品によっては生命保険も形(カタ)に取るなど、それまでの商業銀行の思想とは相容れないものでした。
また、同じ頃には機能別金融の隙間にあった不動産融資にあらゆる金融機関がなだれ込んだ結果、歴史に刻まれるバブル経済が生じてしまいました。そしてバブル経済の崩壊による金融機関の破綻・再編によって、我が国の機能別金融は明確に終焉を迎えたのでした。
そのようななかにあって、名残りなのが銀行とは異なる法律の下にある協同組織金融機関です。現代の金融は営利企業の銀行と非営利の協同組織という区分があり、その違いは必ずしも機能ではないという姿です。その状態で2003年に金融庁主導で展開されたリレーションシップバンキングでは銀行を主要行と地域銀行に分け、地域銀行と非営利協同組織を一緒くたにして中小零細企業向け金融機関にしてしまいました。それはあたかも機能別金融の復活にも見えますが、営利と非営利に同じ行為を期待するような無理筋の施策でした。そのことが、そもそもの金融機能の価値を見失わせる一つの要因になったのはとても残念なことでした。
中小企業向け融資を地方銀行が行うことの必要性は、高度成長期にも数多く指摘されていました。それには主に二つの理由があり、中小企業からさらに成長しようとする企業にとっては非営利協同組織の提供するサービスは十分でないことと、地方銀行は一県一行存在するものの非営利協同組織には空白市町村があることでした。それが相互銀行の普通銀行転換の一つの理由になったわけですが、そのタイミングがバブル経済真っ只中の89年だったのが不幸なことでした。新しく誕生した第二地方銀行は、求められていた中小企業を成長させる融資の空白を埋めることよりも手間暇のかからない不動産融資にのめり込んでしまったのです。
企業全体の99%が中小企業である我が国において、機能としての中小企業融資は永遠のテーマであり、コロナ禍の今、改めてその問題に真剣に向き合う必要があります。そのため、この連載は主に中小企業金融に関心のある人に読んでいただけることを願っています。
筆者プロフィル
1961年広島県生まれ。84年神戸大経営卒、同年広島銀行入行。97年総合企画部課長代理、2006年企画室長、07年担当部長。その後融資企画部長、大阪支店長、リスク統括部長を歴任し、15年10月広島銀行を退職。15年11月金融庁に転職し、初代地域金融企画室長。18年7月より地域金融生産性向上支援室長、19年7月より地域課題解決支援室(21年7月に地域金融支援室に改組)長兼務。21年9月金融庁を定年退職。21年10月日下企業経営相談所代表就任。広島大学大学院人間社会科学研究科客員教授。

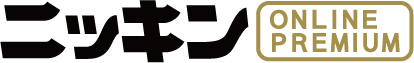
 地域版はこちら
地域版はこちら